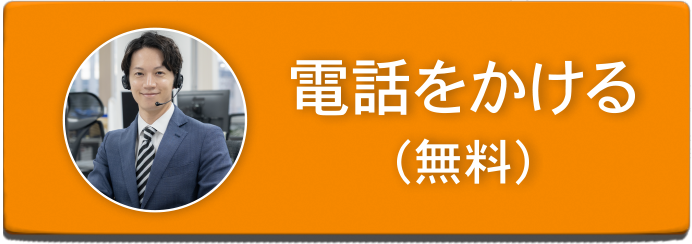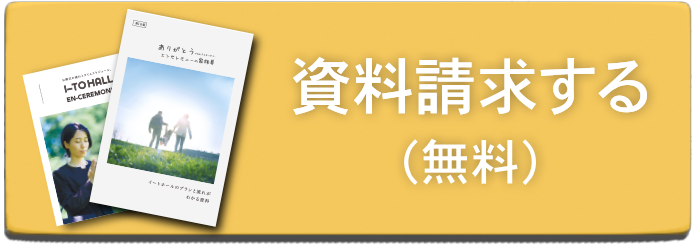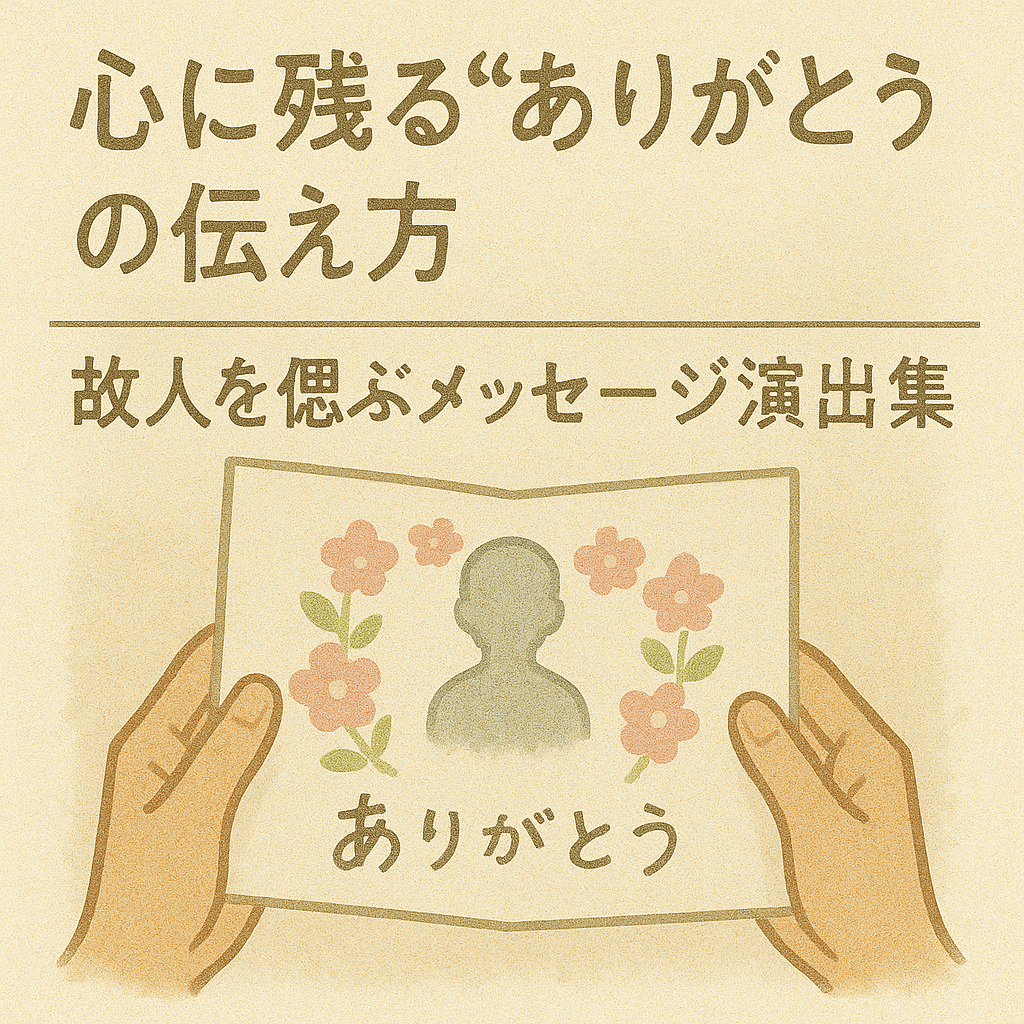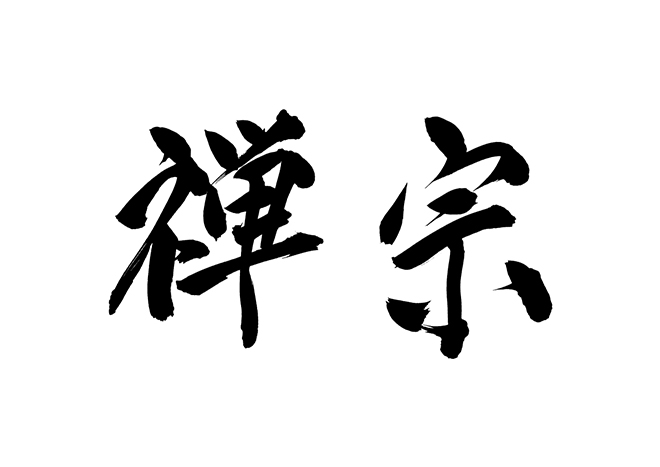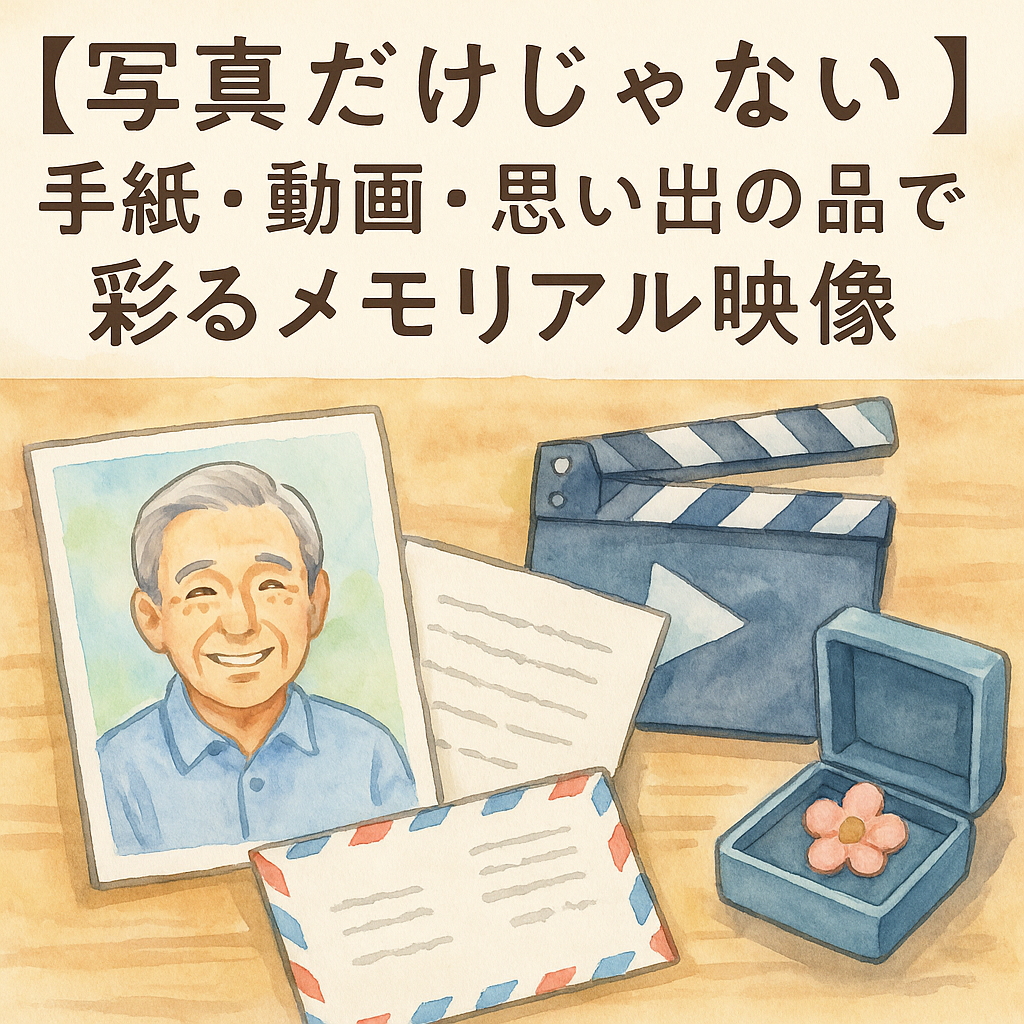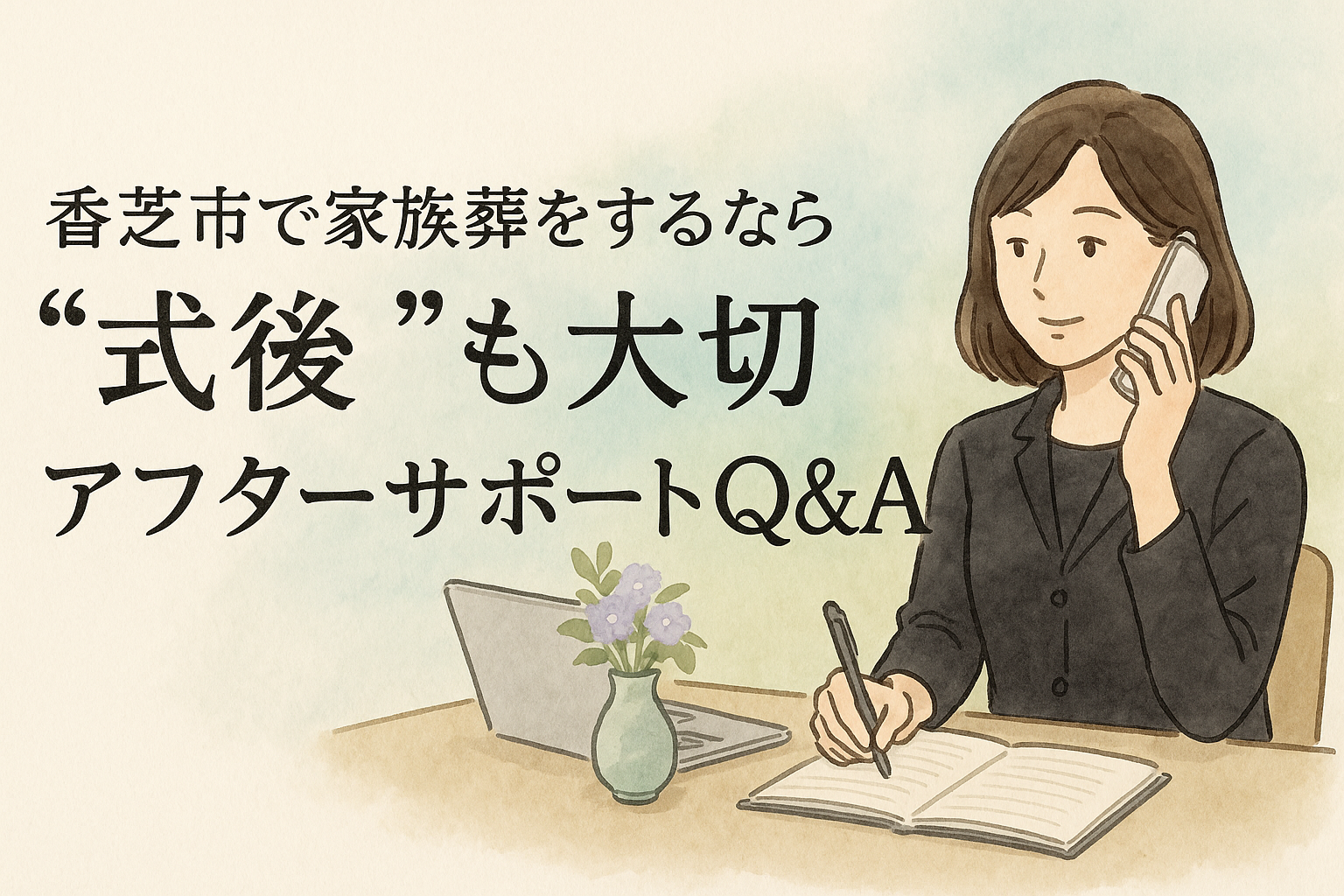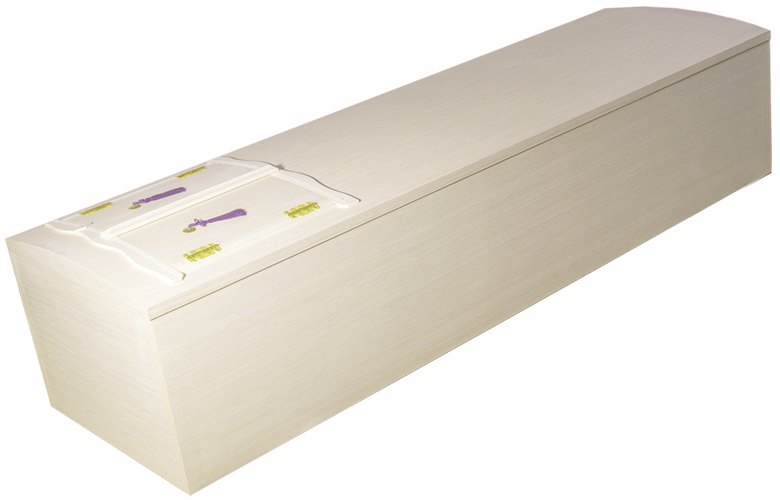骨葬とは? 従来の葬儀との違いをわかりやすく解説|奈良県で家族葬をあげるならエンセレモニー
INFORMATION
お葬式お役立ち情報
2025.02.10
お葬式お役立ち情報
テーマ:
骨葬とは? 従来の葬儀との違いをわかりやすく解説
骨葬とは?メリット・デメリット、流れ、費用をわかりやすく解説
人生の最期をどのように締めくくるか、それは人それぞれです。 従来の葬儀の形にとらわれず、新しい選択肢として「骨葬」という方法があることを知っておきましょう。
まずは、骨葬の基本的な知識から始めましょう。
骨葬は、火葬を先に行い、その後、遺骨を囲んで葬儀や告別式を行うという形式です。 従来の葬儀は、通夜・告別式を行ってから火葬する流れが一般的ですが、骨葬の場合は火葬を先に行うという点が大きな違いです。「故人を偲び、感謝の気持ちを伝える」という葬儀の本質はそのままに、より自由で柔軟な形での お別れを実現できます。
こんな時は骨葬がおすすめ!
骨葬は、従来の葬儀とは異なる点が多いので、「どんな時に骨葬を選べば良いのかわからない…」という方もいるかもしれません。
そこで、ここでは骨葬がおすすめされるケースをいくつかご紹介します。
時間の制約がある
仕事や家族の都合などで、葬儀にかけられる時間が限られている場合もあるでしょう。 骨葬は、火葬を先に行うため、葬儀の日程を自由に設定できます。 時間の融通がききやすいので、忙しい方でも安心です。
遠方からの参列者が多い
遠方から参列者が来る場合、葬儀の日程調整が難しいことがあります。 骨葬であれば、火葬後にゆっくりと日程を決められるので、遠方からの参列者も参加しやすくなります。
故人との最後の時間を大切にしたい
従来の葬儀では、通夜や告別式など、慌ただしく時間が過ぎていく場合も多いです。 骨葬では、火葬前に故人との最後の時間をゆっくりと過ごすことができます。 故人との思い出を振り返り、ゆっくりとお別れをしたい方におすすめです。
感染症のリスクを避けたい
近年、感染症が流行していることもあり、多くの人が集まる葬儀には不安を感じる方もいるかもしれません。 骨葬は、遺体と長時間接触する機会が少ないため、感染症のリスクを低減できます。
宗教的な制約がない
宗教や宗派によっては、骨葬を認めていない場合があります。 しかし、近年では、宗教的な制約にとらわれず、自由な形式で葬儀を行いたいという方も増えています。 骨葬は、宗派にとらわれず、故人らしいお別れを実現したい方にもおすすめです。
簡素な葬儀を希望する
葬儀は、故人を偲び、感謝の気持ちを伝えるための大切な儀式です。しかし、近年では、形式にとらわれず、簡素な葬儀を希望する方も増えています。 骨葬は、シンプルな形式で、故人を見送りたいという方にも適しています。
海外で亡くなった場合
海外で亡くなった場合、遺体を日本に搬送するまでに時間がかかります。 その間、遺体は安置され、葬儀の日程も遅くなってしまうことがあります。 骨葬であれば、海外で火葬を行い、遺骨を日本に持ち帰ってから葬儀を行うことができます。
感染症で亡くなった場合
感染症で亡くなった場合、遺体から感染するリスクがあります。 そのため、遺体との接触を最小限にする必要があります。 骨葬であれば、火葬を先に行うため、感染リスクを抑えることができます。
事件や事故で亡くなった場合
事件や事故で亡くなった場合、遺体の損傷が激しいことがあります。 そのような場合、遺族にとっては、遺体と対面することが辛い場合があります。 骨葬であれば、火葬を先に行うため、遺族の精神的な負担を軽減することができます。
芸能人などの著名な方が亡くなった場合
芸能人などの著名な方が亡くなった場合、多くのファンが葬儀に参列したいと希望することがあります。 しかし、葬儀場が混雑したり、混乱が生じたりする可能性があります。 骨葬であれば、火葬を先に行い、後日、改めてお別れの会を設けることができます。
このように、骨葬は、さまざまな状況に対応できる柔軟な葬儀形式です。
従来の葬儀では対応が難しいケースでも、骨葬であれば、故人や遺族のご希望を叶えることができる場合があります。
骨葬の流れ
1.臨終
2.遺体の搬送
3.火葬
4.葬儀・告別式
従来の葬儀との比較
| 項目 | 従来の葬儀 | 骨葬 |
|---|---|---|
| 火葬のタイミング | 葬儀の後 | 葬儀の前 |
| 葬儀の対象 | 遺体 | 遺骨 |
| 費用 | 高め | 比較的安価 |
| 期間 | 2〜3日 | 1〜2日 |
| 参列者 | 多い | 少なめ |
骨葬のメリット・デメリット
骨葬には、従来の葬儀にはないメリットがある一方、デメリットもあります。 これから骨葬を検討する方は、両方を理解した上で判断することが大切です。
メリット
・時間の融通がききやすい:火葬を先に行うため、葬儀の日程を自由に決められます。
・遠方からの参列がしやすい:葬儀の日程を調整しやすいため、遠方からの参列者も参加しやすくなります。
・故人との最後の時間をゆっくり過ごせる:火葬前にゆっくりお別れをする時間を設けられます。
・感染症のリスクを抑えられる:遺体と長時間接触する機会が減るため、感染症のリスクを抑えられます。
デメリット
・通夜・告別式がない場合がある:骨葬では、通夜や告別式を行わないケースもあります。
・宗教的な制約がある場合がある:宗派によっては、骨葬を認めていない場合があります。骨葬を営む場合、事前に菩提寺にその旨を相談しておくようにしましょう。
・故人と最期に対面できない場合がある:火葬を先に行うため、故人と最期に対面できない場合があります。これは、故人の姿を目に焼き付けておきたいと考える人にとっては、大きなデメリットと言えるでしょう。
骨葬を選ぶ際の注意点
骨葬を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
・宗教・宗派の確認:骨葬が可能な宗教・宗派であるかを確認しましょう。
・葬儀社の選定:骨葬に対応している葬儀社を選びましょう。
・家族や親族との相談:家族や親族とよく相談し、理解を得た上で進めましょう。
・費用について:費用について事前にしっかりと確認しておきましょう。
骨葬に参列する際のマナー
骨葬は、従来の葬儀とは異なる点もありますが、骨葬であっても、参列時のマナーは一般的な葬儀と変わりありません
初めて骨葬に参列する場合は、どのような点に注意すれば良いのか不安に感じる方もいるかもしれません。
そこで、ここでは骨葬に参列する際の基本的なマナーについて解説します。
服装
基本的には、従来の葬儀と同様に、黒や紺などの地味な服装で参列するのが一般的です。
香典
香典は、従来の葬儀と同様に、受付で渡します。
表書きは、「御香典」「御霊前」「御仏前」など、宗派に合わせて選びましょう。
金額の相場は、故人との関係性や年齢によって異なりますが、一般的には、友人や知人の場合は5,000円~1万円、親族の場合は1万円~3万円程度です。
挨拶
遺族への挨拶は、従来の葬儀と同様に、簡潔に行いましょう。
「この度は、ご愁傷様です」「心よりお悔やみ申し上げます」など、気持ちを込めて伝えましょう。
故人との思い出話をする場合は、長々と話さず、短くまとめて伝えるようにしましょう。
まとめ|骨葬は、現代のニーズに合った新しい葬儀のかたち
骨葬は、費用を抑えられたり、時間の融通がききやすいなど、さまざまなメリットがあります。 従来の葬儀にはない自由度の高さが、現代のライフスタイルに合致していると言えるでしょう。
この記事が、骨葬について理解を深めるためのお役に立てれば幸いです。
注釈:
・上記は一般的な骨葬の流れであり、地域や宗教によって異なる場合があります。
・費用は、葬儀社やプラン内容によって異なります。