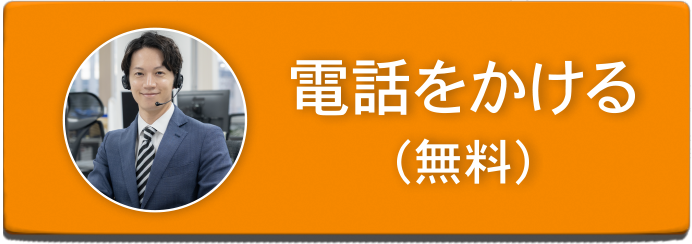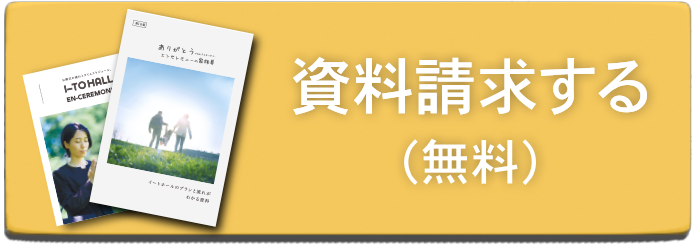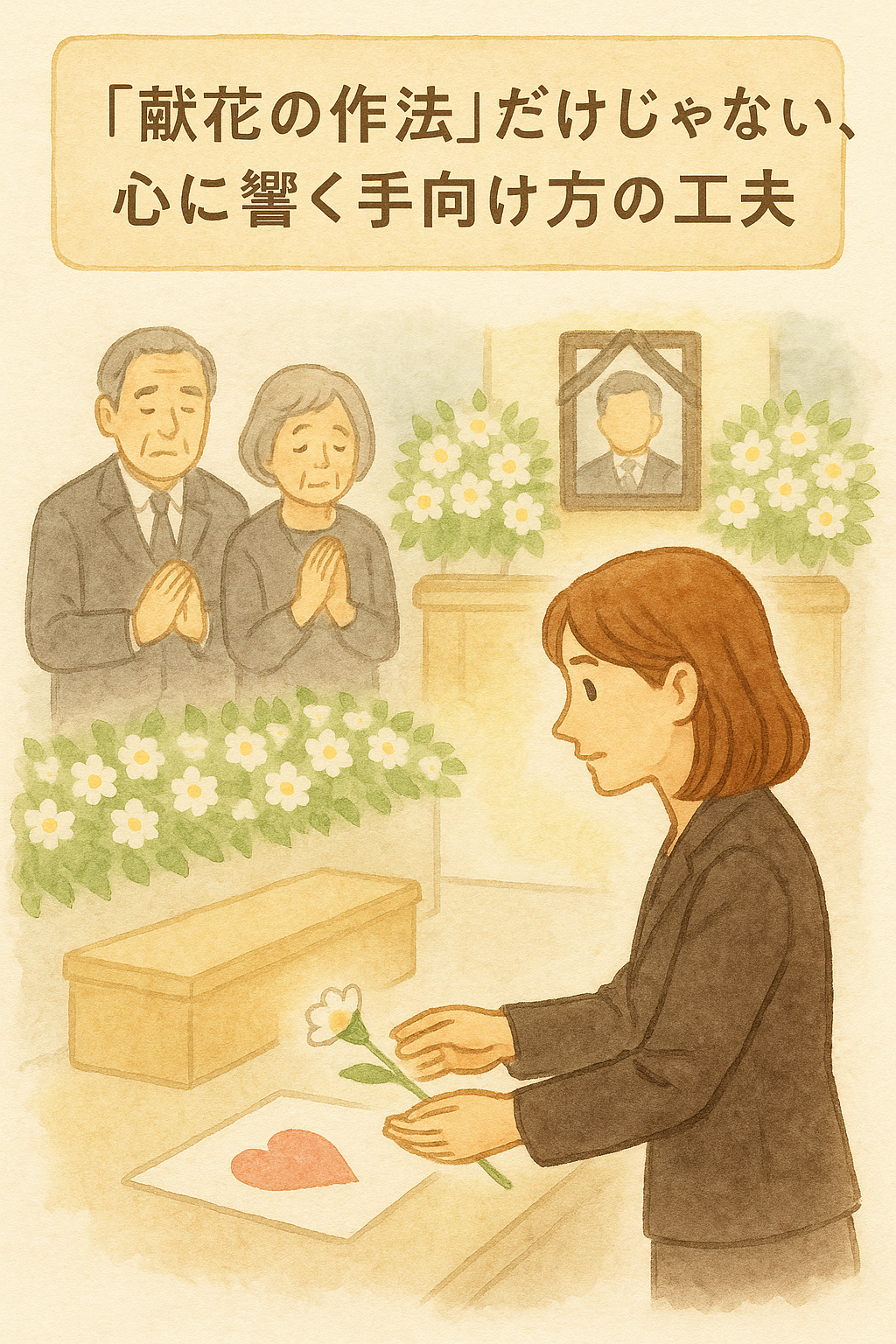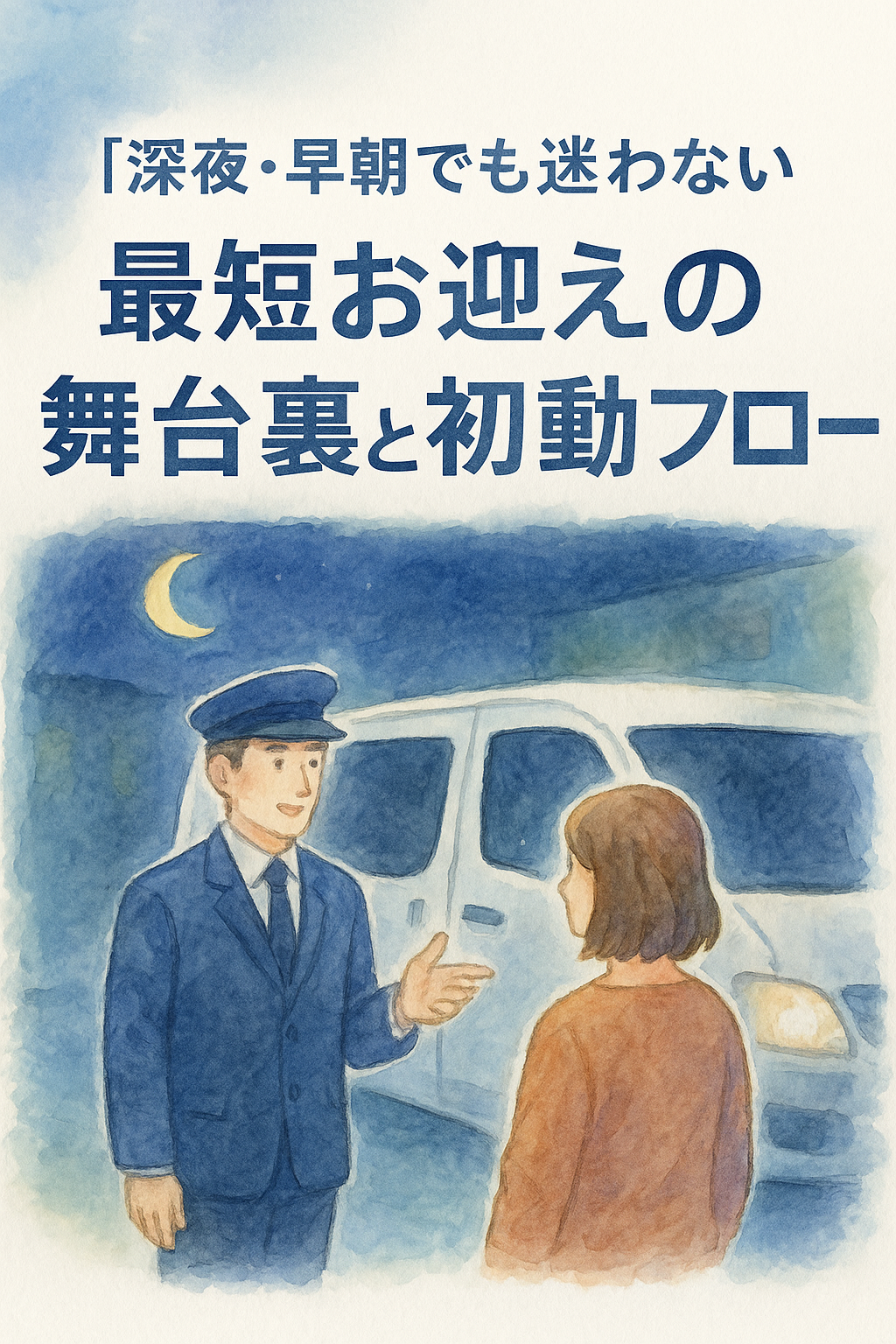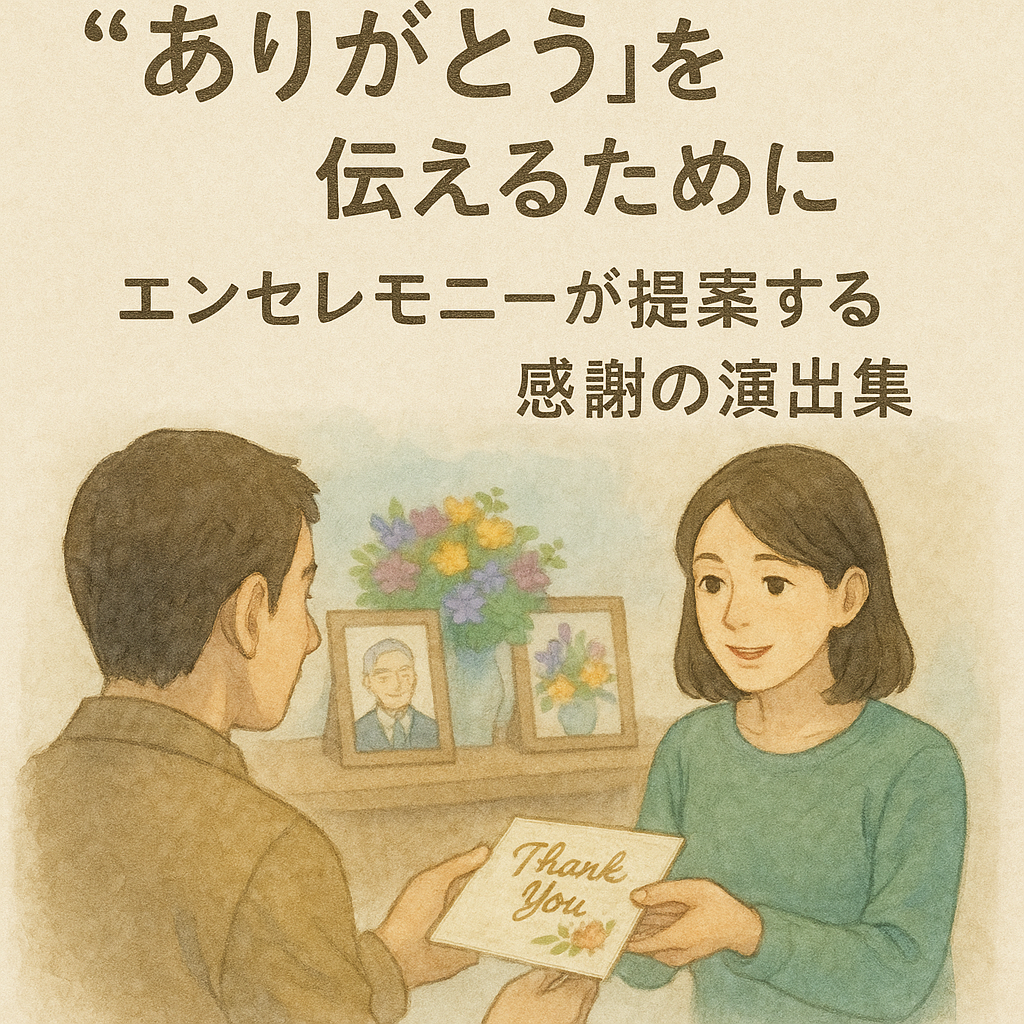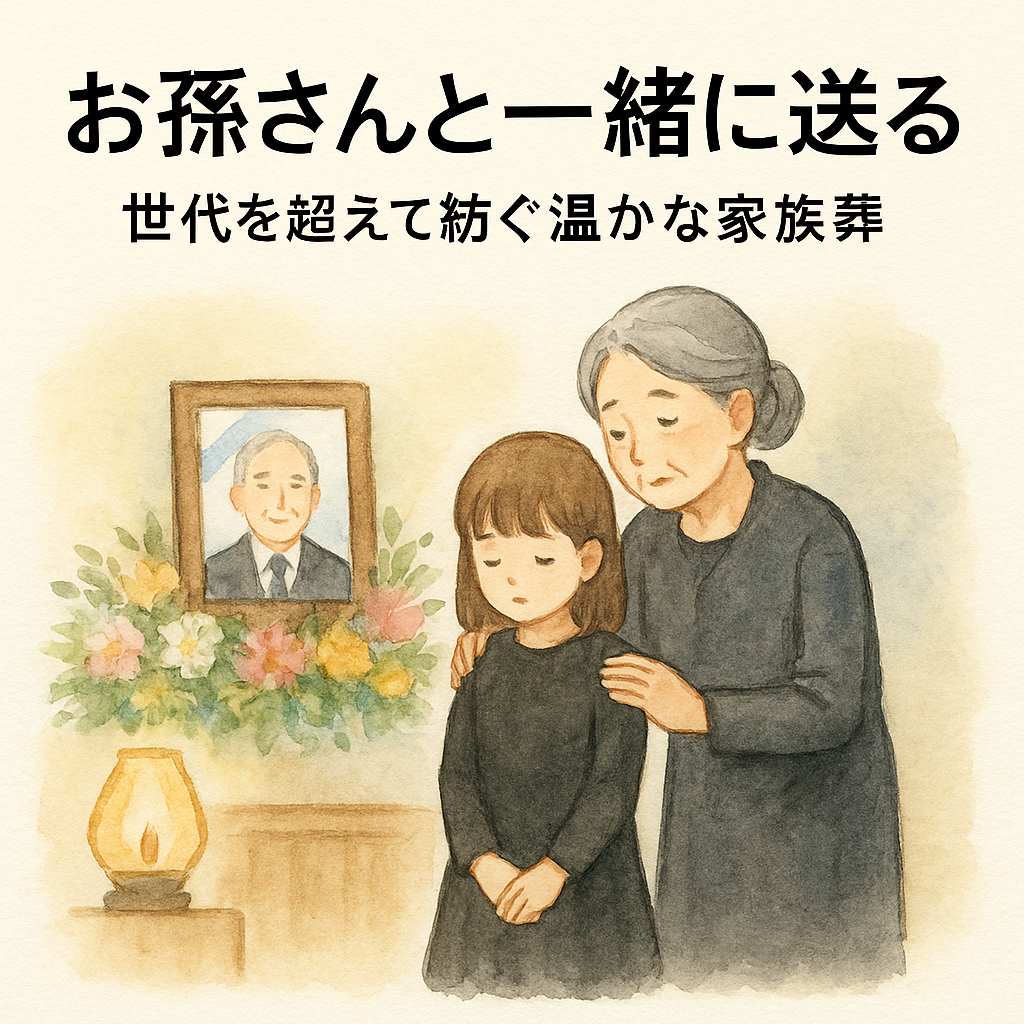浄土真宗のお葬式:流れと特徴、お経の意味を知る|奈良県で家族葬をあげるならエンセレモニー
INFORMATION
お葬式お役立ち情報
2025.02.05
お葬式お役立ち情報
テーマ:
浄土真宗のお葬式:流れと特徴、お経の意味を知る
浄土真宗の葬儀:知っておきたい基礎知識
浄土真宗は、日本で最も信者数の多い仏教宗派の一つです。親鸞聖人を宗祖とし、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることで、阿弥陀如来の力によって極楽浄土に往生できると説いています。
浄土真宗の葬儀は、他の宗派の葬儀とは異なる点が多く、独特の作法や考え方があります。この記事では、浄土真宗の葬儀の流れと特徴、参列する際に知っておきたいマナー、そしてお経の意味について詳しく解説していきます。
浄土真宗の葬儀の特徴
浄土真宗の葬儀は、故人を偲び、遺族が阿弥陀如来の教えに立ち返り、今後の人生を生きていくための儀式という位置づけです。そのため、他の宗派に見られるような、故人の成仏を願うための儀式とは、考え方が異なります。
主な特徴は以下の通りです。
・葬儀は「お別れ会」: 故人は亡くなった時点で極楽浄土へ往生していると考えられているため、葬儀は故人の成仏を願う儀式ではなく、遺族や親族、知人が故人を偲び、別れを告げる「お別れ会」のようなものです。
・戒名ではなく法名: 浄土真宗では、戒名ではなく法名を用います。戒名は、生前に授戒を受け、仏弟子となった証として与えられる名前ですが、浄土真宗では、すべての人が阿弥陀如来の力で救済されると考えるため、戒律を守る必要がなく、戒名も用いません。
・焼香は1回: 浄土真宗では、焼香は1回のみ行います。これは、故人の成仏を願うためではなく、阿弥陀如来への感謝と敬意を表すためです。
・読経の内容: 浄土真宗では、「正信偈」や「阿弥陀経」など、浄土真宗の教えを説いたお経が読まれます。
・お供え物: 故人が生前に好きだったものを供えることは避け、蓮の花や和菓子などを供えるのが一般的です。
浄土真宗の葬儀の流れ
浄土真宗の葬儀は、一般的に以下の流れで行われます。
1.臨終勤行: 亡くなった直後に、僧侶が枕元で読経を行います。
2.通夜: 遺族や親族、近親者が集まり、故人を偲びます。浄土真宗では、通夜振る舞いを行わない場合もあります。
3.葬儀: 僧侶による読経、焼香、法話などが行われます。葬儀後に出棺し、火葬場へ向かいます。
4.火葬: 火葬後、遺骨を拾い、骨壺に納めます。
5.初七日法要: 浄土真宗では、初七日法要を葬儀と同時に行うことが一般的です。
6.精進落とし: 葬儀・初七日法要後、参列者で食事を共にすることで、故人を偲びます。
7.後飾り: 遺骨を自宅に安置し、四十九日法要まで供養します。
8.四十九日法要: 故人が亡くなってから四十九日目に行われる法要です。
9.納骨: 四十九日法要後、遺骨を墓地に納骨します。
10.年忌法要: 一周忌、三回忌、七回忌など、年忌に法要を行います。
浄土真宗のお経とその意味
浄土真宗で読まれるお経は、主に以下の3つです。
①正信偈(しょうしんげ):親鸞聖人が、浄土真宗の教えを七言偈の形でまとめたものです。浄土真宗で最も重要な経典とされています。
意味: 阿弥陀如来の本願力によって、すべての衆生が救済されることを説いています。
②阿弥陀経(あみだきょう):浄土三部経の一つで、阿弥陀如来と極楽浄土の様子が詳しく説かれています。
意味: 極楽浄土は、苦しみのない、喜びに満ちた世界であることが説かれています。
③和讃(わさん): 仏徳を讃える歌。様々な種類があり、法要の内容に合わせて選ばれます。
意味: 阿弥陀如来の慈悲や、浄土真宗の教えを分かりやすく伝えています。
これらの他に、
・仏説阿弥陀経(ぶっせつあみだきょう)
・観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)
・無量寿経(むりょうじゅきょう)
なども読まれることがあります。
浄土真宗のお経は、漢文で書かれており、難しい言葉も多いですが、僧侶が分かりやすく解説してくれる場合もありますので、耳を傾けてみましょう。
浄土真宗の葬儀で知っておきたいマナー
浄土真宗の葬儀に参列する際は、以下のマナーに注意しましょう。
・服装: 黒の礼服を着用するのが基本です。平服で参列する場合は、地味な服装を選びましょう。
・数珠: 浄土真宗では、どの宗派の数珠でも構いません。数珠を持っていない場合は、なくても失礼にはあたりません。
・焼香: 焼香は1回のみ行います。焼香の回数は、宗派によって異なるため、注意が必要です。
・合掌: 浄土真宗では、合掌する際に指を離して合掌します。これは、阿弥陀如来にすべてを委ねるという意味が込められています。
・言葉遣い: 浄土真宗では、「ご冥福をお祈りします」などの言葉は使いません。故人はすでに極楽浄土へ往生していると考えられているため、「お浄土へお帰りになられました」などと言うのが適切です。
・香典: 香典袋の水引は、黒白または双銀の結び切りを選びます。表書きは「御香典」または「御仏前」とします。
・供花: 白や黄色の菊の花をメインとした供花が一般的です。
・その他: 浄土真宗では、葬儀や法要の際に、読経に合わせて合掌したり、礼拝したりすることはありません。
浄土真宗の葬儀に関するQ&A
Q. 浄土真宗の葬儀では、なぜ「ご冥福をお祈りします」と言ってはいけないのですか?
A. 浄土真宗では、人は亡くなった時点で阿弥陀如来の力によって極楽浄土へ往生すると考えられています。そのため、「ご冥福をお祈りします」のように、故人の成仏を願う言葉は使いません。
Q. 浄土真宗の葬儀に参列する際、数珠は必要ですか?
A. 浄土真宗では、どの宗派の数珠でも構いません。数珠を持っていない場合は、なくても失礼にはあたりません。
Q. 浄土真宗の葬儀で、焼香は何回すればいいですか?
A. 浄土真宗では、焼香は1回のみ行います。
Q. 浄土真宗の葬儀で、香典の表書きはどうすればいいですか?
A. 「御香典」または「御仏前」とします。
まとめ
浄土真宗の葬儀は、他の宗派の葬儀とは異なる点が多く、独特の作法や考え方があります。この記事で紹介した内容を参考に、浄土真宗の葬儀に参列する際は、失礼のないようマナーを守りましょう。
参考資料
・浄土真宗本願寺派 https://www.hongwanji.or.jp/
・真宗大谷派 https://www.higashihonganji.or.jp/
注記
この記事では、浄土真宗の葬儀について一般的な情報を解説しましたが、地域や寺院によって、慣習や作法が異なる場合があります。葬儀に参列する際は、事前に葬儀社や寺院に確認することをおすすめします。