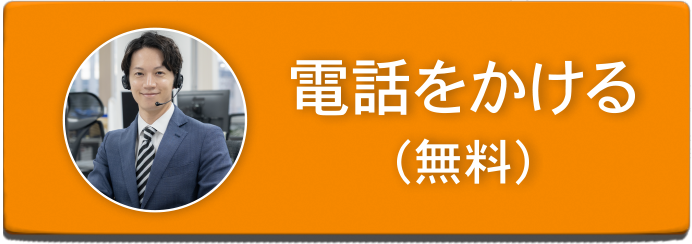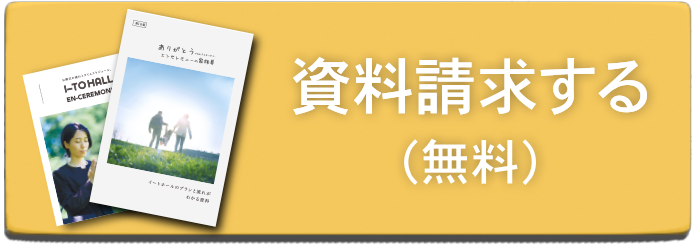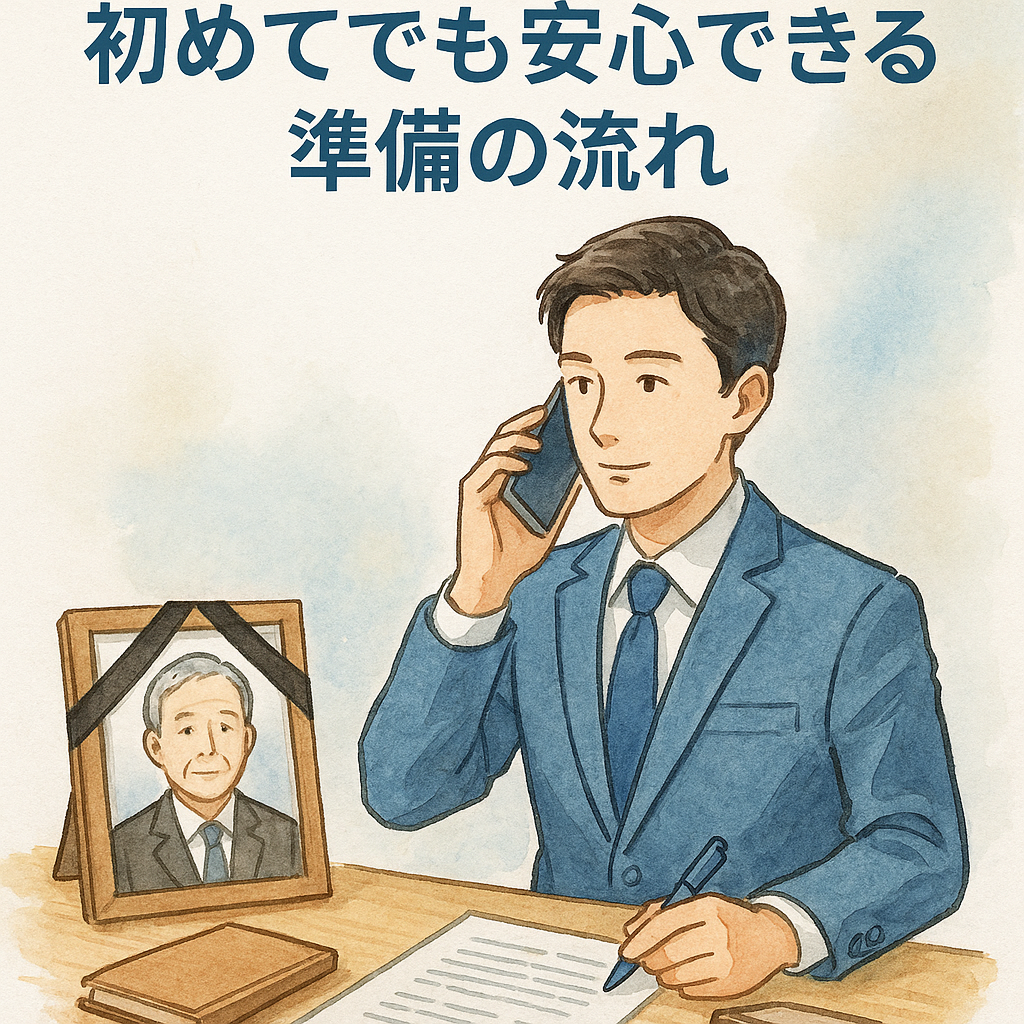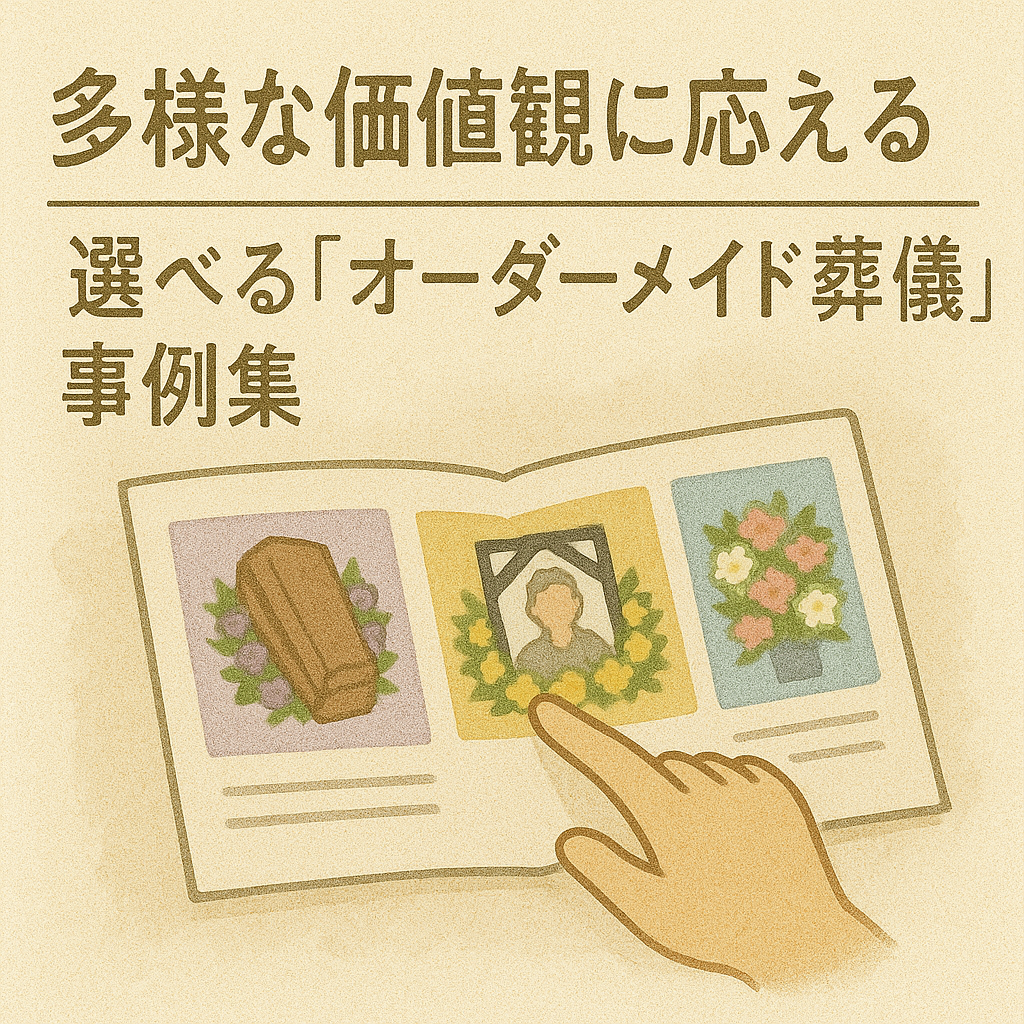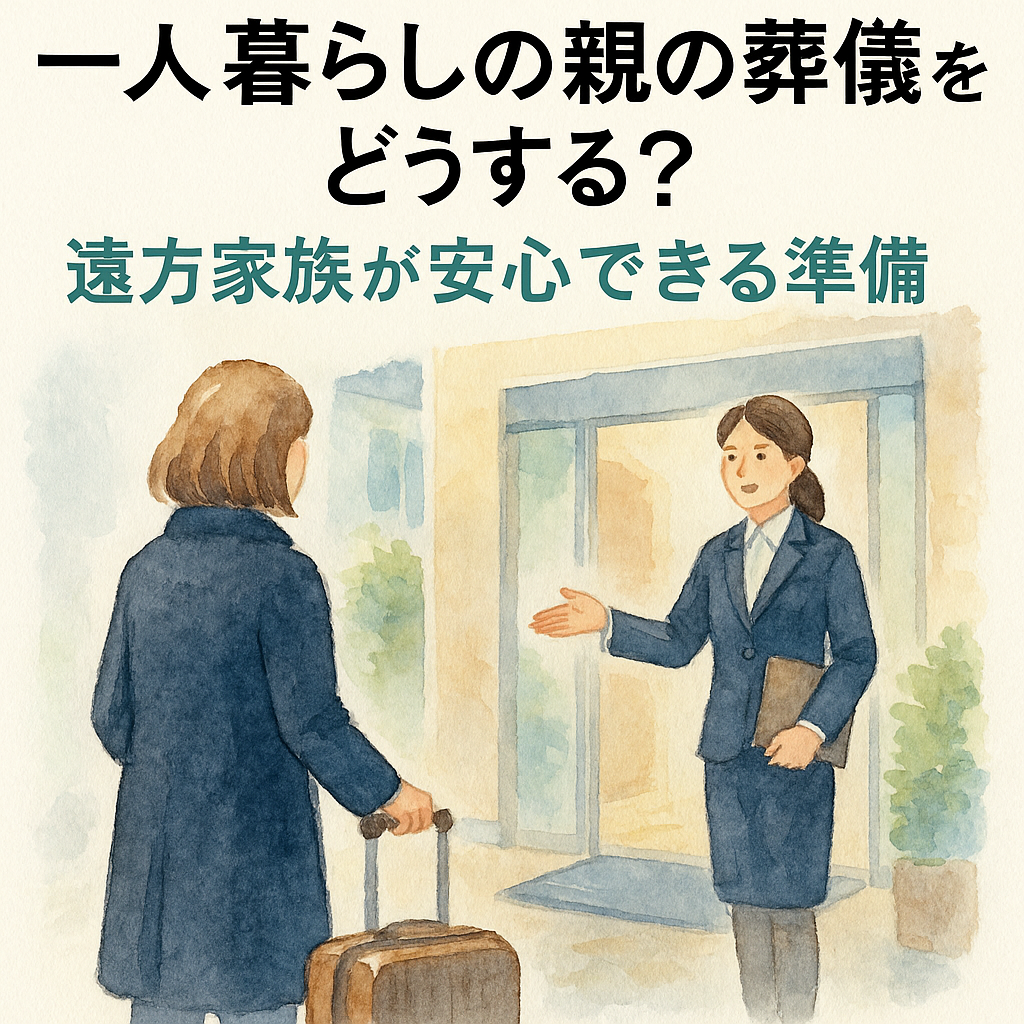葬儀にどこまでの親族を呼ぶ?~親族の招待を限定する場合のマナーも解説~|奈良県で家族葬をあげるならエンセレモニー
INFORMATION
お葬式お役立ち情報
2024.12.20
お葬式お役立ち情報
テーマ:
葬儀にどこまでの親族を呼ぶ?~親族の招待を限定する場合のマナーも解説~
親族とは?
親族は法律や社会的関係に基づき定義される、血縁や姻族(婚姻によってつながる家族)を含む広い意味の家族関係を指します。
法的定義
日本の民法では、親族は次のように分類されています:
血族:直接の血縁関係のある人(親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫など)。
姻族:配偶者の血族(義理の親、義理の兄弟など)。
直系・傍系:直系は親子や祖父母など上下に続く関係、傍系は兄弟やおじ・おばなど横に広がる関係。
親族の範囲
法律上の範囲:6親等以内の血族、3親等以内の姻族が「親族」に該当します。
日常生活での範囲:実際には近い親族(親、兄弟、叔父・叔母など)を指すことが多いです。
遺族とは?
遺族は、亡くなった人(故人)と特に深い関係にあり、精神的または経済的に故人の影響を受ける人々を指します。
主な特徴
- 遺族は一般的に、故人の配偶者、子、両親、兄弟姉妹など、故人の生活に密接に関わっていた人々が含まれます。
- 遺族の範囲には、法的な血縁関係や姻族関係が影響する場合もありますが、同居していた人や生活を共にしていた人も含まれることがあります。
遺族の役割
遺族は葬儀や遺産相続、弔意を受ける中心的な立場になります。例えば:
- 葬儀の喪主として故人を送り出す責任を負う。
- 故人の財産を分割する「法定相続人」に該当する場合が多い。
- 心理的な喪失感を抱えることから、精神的ケアや支援を受ける対象にもなります。
親族と遺族の違い
| 項目 | 親族 | 遺族 |
|---|---|---|
| 範囲 | 血縁・姻族を含む幅広い家族関係 | 故人と特に近しい関係にある人々 |
| 法的基準 | 民法で6親等以内の血族、3親等以内の姻族と規定 | 特に法的定義はなく、状況により異なる |
| 役割 | 家族全体としての関係性 | 故人を悼む中心的な存在、相続や葬儀に関与 |
親族と遺族に関する注意点
- 葬儀の場での扱い
葬儀では親族が参列者として招かれますが、遺族は弔問を受ける立場にあることが多いです。親族の中でも、特に遺族は心情を配慮した行動が求められます。
法的手続き
・遺産相続や年金の手続きでは、遺族であるかどうかが重要です。
・親族であっても、相続権がない場合があります(例:遠い親族)。
心理的サポート
・遺族は心理的負担が大きくなるため、親族や周囲からの支援が必要です。
葬儀に呼ぶ親族の範囲は?
葬儀に、どこまでの範囲の親族を呼べばいいのか悩まれる方も多いと思います。
葬儀に呼ぶ親族の範囲について明確な決まりはありません。
近しい親族であっても、不仲であるとか交流が全くない場合は、呼ばないこともあるでしょう。
一方で、遠い親戚であっても、普段から付き合いが深い場合は、葬儀にきていただきたものです。
人の繋がりというものは、血縁関係の濃さだけでは計ることはできません。
そのため、あくまでも一般論で、葬儀に呼ぶ親族の範囲を想定してみます。
家族葬の場合
家族だけで、故人を静かに見送りたい場合もあるでしょう。
その場合に葬儀に参列するのは、故人からみて配偶者と子供、両親と兄弟姉妹等に限定されるでしょう。
概ね10名程度で、葬儀を行うことになります。
30名程度参列の葬儀の場合
30名程度で葬儀を行う場合は、家族葬に参列する遺族に加えて、呼ぶ人の範囲も広がります。
具体的には、祖父母や孫、甥や姪、従姉妹などです。
また配偶者の家族を呼ぶことも一般的です。
一般の葬儀の場合
遺族や親族に加えて、友人や知人も参列する葬儀の場合、より多くの親族も呼ぶことになります。
法律的に明記されている親族とは、六親等までの血縁者と、三親等までの姻族までです。具体的には、故人の曽祖父母の甥姪やはとこ、従姉妹の曾孫などが六親等にあたります。
三親等の姻族とは、配偶者の叔父叔母や甥姪、曾孫の配偶者や甥姪の配偶者などです。
もちろんこれらの人々を、必ずしも全員呼ぶ必要はありません。
この範囲内で付き合いのある人、お世話になった方に声を掛ければいいでしょう。
親族の招待を限定する場合のマナー
葬儀に招待する親族を限定する場合、相手に配慮した対応が大切です。限られた招待となる理由を適切に説明し、誤解や感情の摩擦を避ける工夫が求められます。以下に具体的なマナーを挙げます。
1. 招待を限定する理由を明確に伝える
招待する親族を絞る際は、その理由を正直に伝えます。例えば:
- 経済的事情:「規模を縮小せざるを得ない状況です。」
- 場所の制約:「式場のキャパシティの関係で少人数での実施となります。」
- 故人の意向:「生前、近しい人たちだけで静かに見送りたいと話していました。」
言葉を選び、相手が納得できるよう誠実に説明することが大切です。
2. 書面や電話での案内
参列をお願いしない場合でも、事後報告やお知らせを忘れないようにします。
- 書面での案内:簡潔なお知らせ状で事情を伝える。
- 電話での説明:親しい間柄であれば直接電話をかけて伝える。
これにより、相手に対して配慮が感じられる対応となります。
3. 別途お別れの機会を設ける
葬儀に参列できなかった親族のために、お別れの場を別途設けることも一案です。
- 自宅での法要や献花の場を設ける。
- 故人の写真や記録を共有するなどの工夫をする。
これにより、葬儀に参加できなかった方々も故人を偲ぶ機会を得ることができます。
4. 返礼や感謝の気持ちを伝える
招待を限定した場合でも、気にかけてくれた親族に対して感謝の気持ちを伝えることが大切です。
- 礼状を送る:お悔やみをいただいた場合には礼状を送ります。
- 香典返し:香典を受け取った場合、通常どおり返礼品を送ります。
まとめ
遺族と親族の違いを理解し、葬儀における親族招待の基準を考えることは、円滑な進行と参列者の満足感を得るために重要です。特に親族を限定して招待する場合は、丁寧で配慮ある説明と対応を心がけましょう。
もし招待範囲や進め方について迷う場合は、葬儀社や専門家に相談することで、状況に応じた適切なアドバイスを得ることができます。